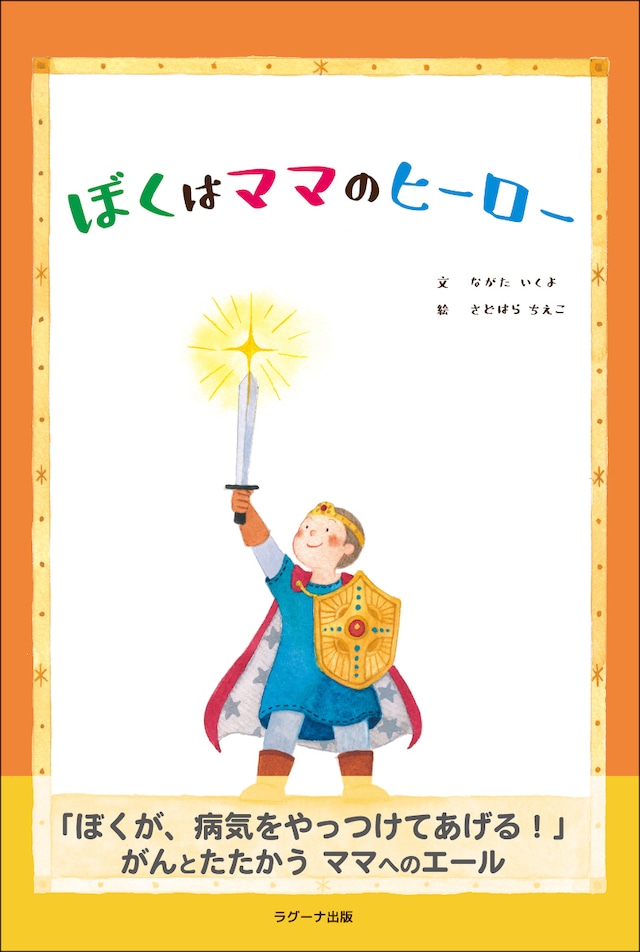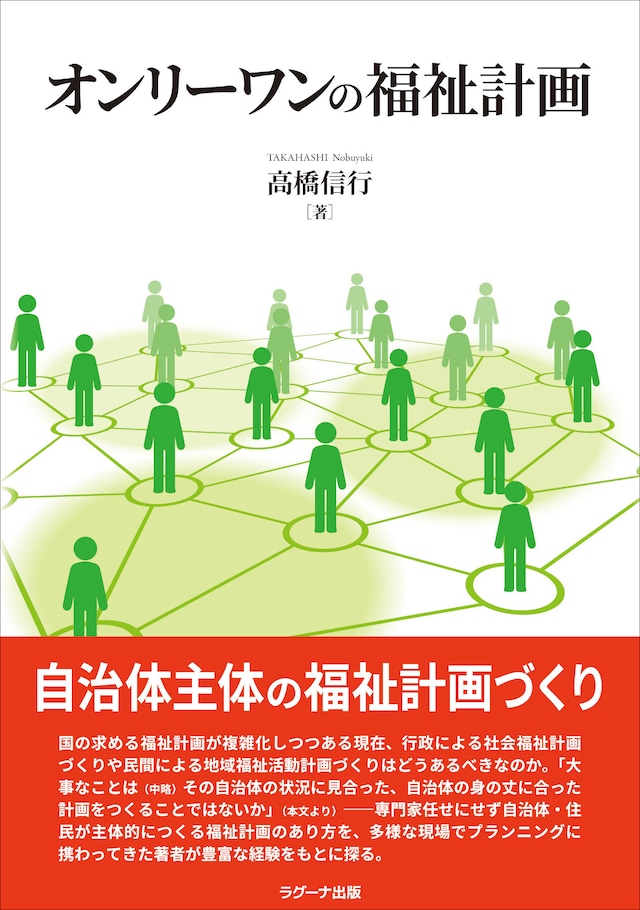ガイドライン 社会教育施設における障がい者の学びの場づくり ―「誰もが学べる」生涯学習の発展に向けて
地域の社会教育施設を「誰もが学べる場」とするために
本書のテーマは、大きく二つの柱から成る。「障がい者、ひいてはすべての人々の生涯学習の場を広げるには」、そして「社会教育施設をいかに『学びの場』としていくか」という問題意識である。
障がいへの理解を深め、既存のリソースを活用し、さらには場に集う人々の「ともに」という感覚を大切にする。「……サービス提供にあたっては『理解』よりも、人間が肌感覚で持っているであろうケアの認識を確認するのが先決だ。この心持ちがあって初めて理解が進むとのプロセスを確認したい」(本書「おわりに」より)。その帰結として、地域における豊かな文化生活の実現が可能となる。
著者による現場での聞き取りを含む調査、議論や対話に基づく豊富な情報・事例をコンパクトにまとめ、巻末にはグループディスカッションなどに便利な「研修用整理ノート」を掲載。地域の社会教育施設を活用し、豊かな障がい者の学びや生涯学習を実現するうえで、必携のガイドライン。
※本書は、令和5(2023)年度文部科学省「地域連携による障害者の生涯学習機会の拡大促進」事業においてみんなの大学校が実施した「各種障がいへのオンラインでの学びとSDGs講座及び指定管理業者との場づくり研究」の成果物をベースとし、一部加筆訂正したものです。
引地 達也 著 A5判並製 104ページ
ISBN978-4-910372-49-5 C0036
定価1,100円(本体1,000円+税)
2025年10月1日発行
【目次より】
○はじめに
1 インクルーシブな「学び」の可能性を視野に置いた運営
(1)「学び」とは何かの確認──どんな障がいでも成立する学び
(2)文部科学省の政策及び方向性の確認──国が求める社会教育施設の役割
(3)障がい者に関する国際基準の確認──障害者権利条約を理解する
2 障がいへの理解促進を実証的に進める
(1)行政区分の3障がいへの理解──知的・精神・身体のそれぞれの特性について
(2)重症心身障がい者について──医療的ケアが必要な障がい者の特性と対応
(3)発達障がいについて──発達障がいを細分化し、適切な対応を理解する
3 オープンな施設・イベントを企画する
(1)青年学級の歴史と課題──公民館が展開してきた「青年学級」から学ぶ
(2)芸術活動と障がいに関する知見を高める──芸術作品制作や音楽、演劇などの活動と障がい者の取り組みに関する全国の事例を参考にする
(3)オープンイベントの事例検討──オープンキャンパスなど、運営状況の詳細から検討する
4 地域に根差した障がい者への適切なアプローチを検証する
(1)地域での福祉の成り立ちへの理解──各地域での福祉行政とのコミュニケーションを会得する
(2)福祉サービス区分と障がいの現状──福祉行政への理解を深め連携の素地を確保する
(3)アプローチの方法について──地域で障がい者が置かれている状況を理解し適切なアプローチを考える知見を養う
5 民間企業の役割を検討し、関係機関及び専門家と連携しながらダイバーシティ社会の場づくりを探究する
(1)民間企業としての役割の再確認──企業の特性を生かした取り組みを推進
(2)地域での事例と考え方・動き方から学ぶ──自治体・NPO(市民)主体編
(3)地域での事例と考え方・動き方から学ぶ──医療法人・学校法人主体編
◇トークセッション「社会教育施設の作り方・考え方・動き方」(青木雅樹・引地達也)
○研修用整理ノート/参考文献/おわりに
《コラム「障がい者の生涯学習の風景」》
1 「おんがくのじかん」の「重症心身障がい」者の反応を社会で共有する
2 藤沢市のメタバースが描く未来
3 障がい者の就労とキャリアアップ
4 重症心身障がい者と「学び」の枠組み
5 秋田の熟議が生む垣根のない生涯学習
6 地域のリソースを生かす──松山の俳句
7 重度障がいの「進路」を考える柔軟性と可能性
8 「はっぴーそんぐ」を共有して生まれるハッピーを感じて
9 調理メニューの豊富さ、完璧な味が「学び」の証し
○著者
引地達也(ひきち・たつや)
フェリス女学院大学准教授、上智大学大学院博士後期課程修了、博士(新聞学)、文部科学省障害者生涯学習推進アドバイザー、一般社団法人みんなの大学校代表理事・学長。ケアメディアラボ共同代表。
著書に『ケアメディア論――孤立化した時代を「つなぐ」志向』(ラグーナ出版、2020年)、『わたしたちのケアメディア──誰もが生きやすい社会のコミュニケーション』(晶文社、2025年)、編著に『それでも一緒に歩いていく――牧ノ原やまばと学園50年の歩み』(ラグーナ出版、2021年)、『障がいのある人びとの学びをどのようにデザインするか』(海老田大五朗編、学文社、2025年)など。
○協力
青木雅樹(あおき・まさき)
サントリーパブリシティサービス株式会社 シニア・スペシャリスト。一般社団法人もらいパートナーズ理事、学校法人茂来学園評議員、障がい者雇用支援センター評議員。